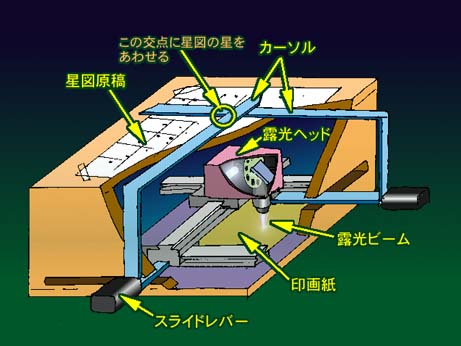
つける。コンピュータ制御の技術を持たなかった当時の私とし
、手動で原稿をならう方式しか考えられなかった。この装置は
材料集めと一部の組立まで進めたが、その後の原寸露光用マイ
クロプロッターのアイディアにとって代わられ、完成をみるこ
とはなかった。いわば幻の装置となった。
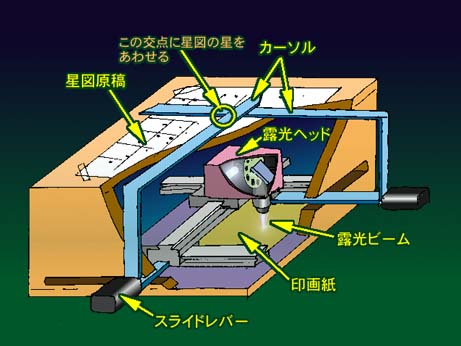 |
|
つける。コンピュータ制御の技術を持たなかった当時の私とし 、手動で原稿をならう方式しか考えられなかった。この装置は 材料集めと一部の組立まで進めたが、その後の原寸露光用マイ クロプロッターのアイディアにとって代わられ、完成をみるこ とはなかった。いわば幻の装置となった。 |